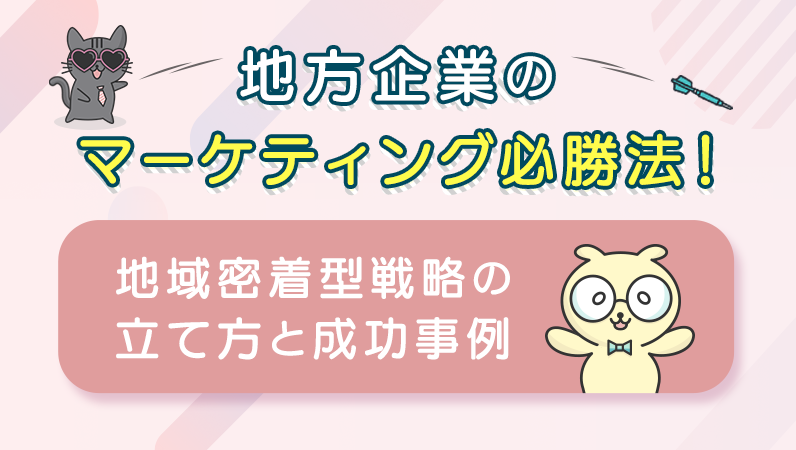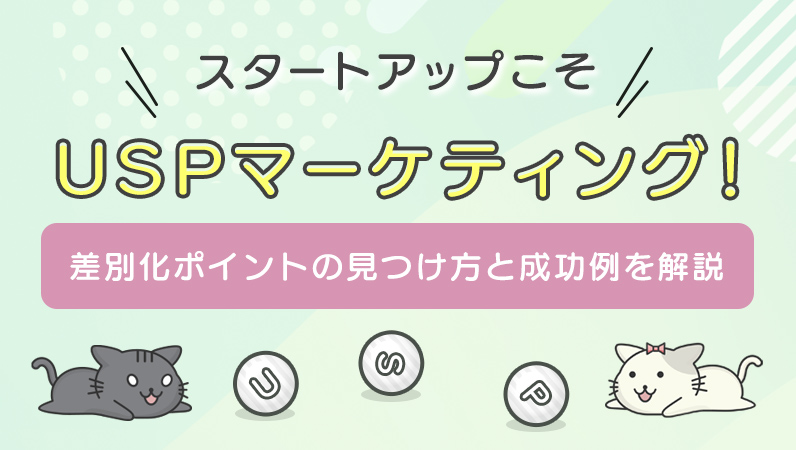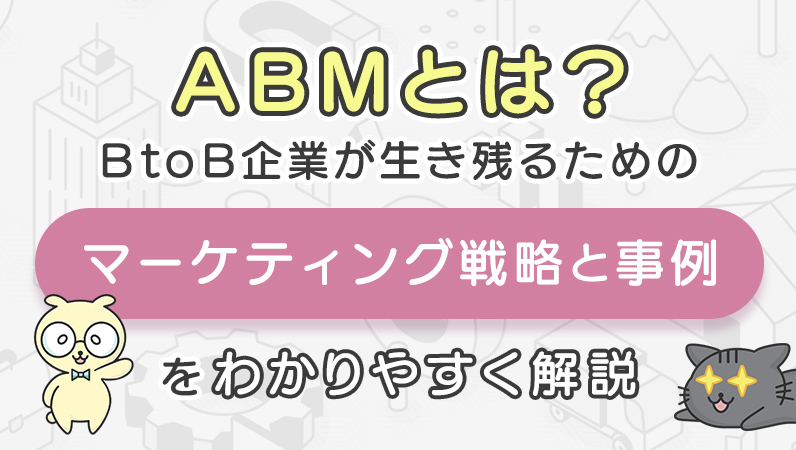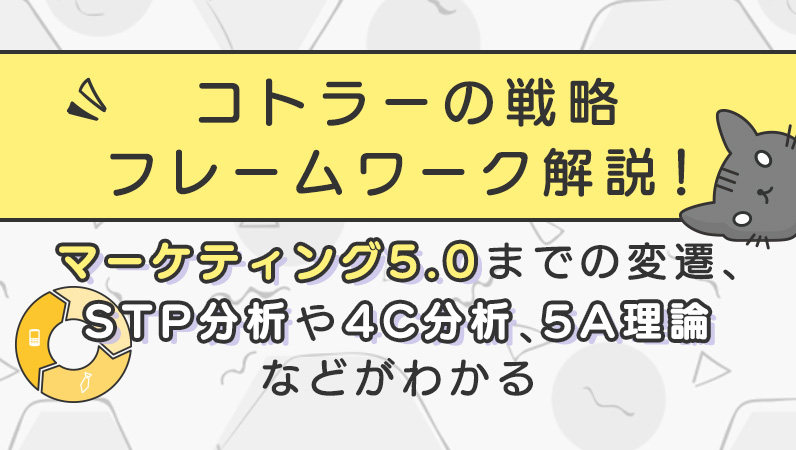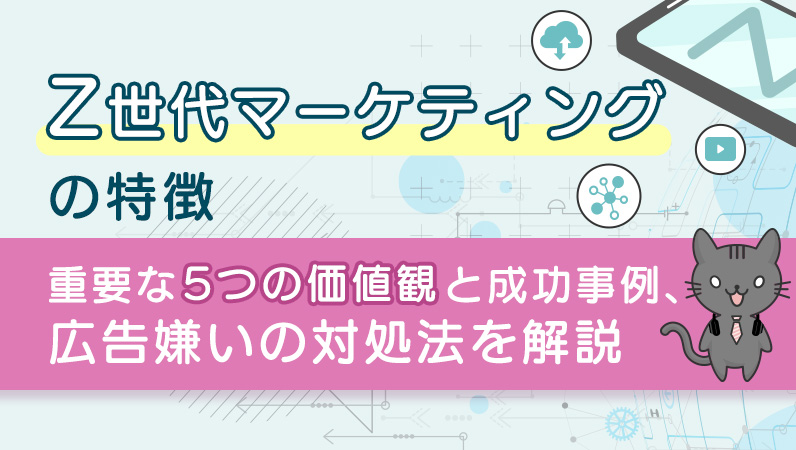NPS(Net Promoter Score)とは、簡単にいうと「お客さまが企業やブランドに対して抱いている愛着度や信頼度の高さ」を判断するための指標です。
この記事では、これからますます注目度が高まっていくNPSについてやさしく解説します。
NPSはマーケティングにどう活用できるの?調査や計算方法は?そんな疑問を解消して、ビジネスでNPSを活用してみましょう。
先輩、最近「NPS」っていうのが話題だって聞いたんですけど、どういうものなのか知っていますか!?
おぉ、さすがビギニャー君。しっかりと情報収集していて感心感心。NPSは欧米でよく知られているマーケティング指標のひとつなんだけど、最近は日本でも注目を集めるようになったんだよ。
へぇ、そうなんですね!やっぱりシニヤン先輩は物知りですね~。詳しく教えてほしいです!
NPS®とは?

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。
NPS®(以下、NPS)は、企業における顧客ロイヤルティを測るための指標です。2003年にフレドリック・F・ライクヘルド氏によって発表されました。
欧米の公開企業において3分の1以上が活用しているといわれるほど海外ではメジャーな指標で、日本でも最近少しずつ注目を集めています。
これだけを聞いても、どのような指標でどのような効果があるのかを理解できない方は多いかもしれません。ここでは、NPSの意味をわかりやすく解説します。
- NPSを簡単にいうと?
- NPSと顧客満足度(CS)の違い
- あわせて押さえておきたい「eNPS」とは
上記の3つのポイントを詳しくみていきましょう。
NPSを簡単にいうと?
NPS(Net Promoter Score:ネットプロモータースコア)とは、お客さまが企業やブランドに対して抱いている愛着度や信頼度の高さ(顧客ロイヤルティ)を測るための指標です。ブランディングの効果を測定する有用なKPIとして、しばしば用いられます。
商品・サービスや企業自体を家族や友人におすすめしたいかどうかをスコア化し、顧客にどれほど愛着や信頼を抱いてもらえているのかを調査します。NPSは、顧客体験の評価・改善に活用することが可能です。企業の業績や成長性と関連性が深く、今後の収益予想や経営判断に役立つとされています。
NPSの種類
一言でNPSといっても、その種類や調査の種類はさまざまです。NPSには、「絶対NPS」と「相対NPS」の2種類があります。絶対NPSとは、すべての業界のNPSスコアに対して、同一の基準で良し悪しを判断する手法です。
例えば、スコアが0未満の場合は「悪い評価」、スコアが50以上であれば「非常に良好な評価」など、業界を問わずスコアの値だけで評価します。
対して「相対NPS」は、業界内の競合他社と比較して自社スコアを見る方法です。業界の平均スコアや競合他社のスコアと比較し、どれほど劣っているのか・優れているのかを評価します。
NPSの調査方法や数値の傾向は業界によって異なるため、絶対NPSだけを用いて評価することはあまり現実的ではありません。評価の際は、相対NPSを用いることを推奨します。
NPS調査の種類
NPSの調査方法にも、「トランザクション調査」と「リレーショナル調査」という2つの種類があります。トランザクション調査とは、顧客が何らかの利用体験をしたあとに実施するNPS調査です。例えば、店舗で商品を購入したりサービスを利用したりした直後に行われる調査が該当します。
定常的に行われることが多い調査で、顧客体験を評価してもらうことで、提供サービスの課題発見につなげることを目的としています。
対してリレーショナル調査とは、顧客が自社ブランドで体験する全体的な体験を評価するためのNPS調査です。ブランドを総合的に評価してもらい、全体的な満足度を把握することを目的としています。
年に1~2回などの頻度で定期的に実施することが一般的です。両方の調査を実施することで、各タッチポイントにおける顧客ロイヤルティがブランド全体に与える影響を分析しやすくなります。
NPSと顧客満足度(CS)の違い
NPSと顧客満足度(CS)の違いは、業績に直結するかどうかというポイントです。両者はどちらも顧客ロイヤルティを測る指標ですが、調査の内容が少し異なります。
顧客満足度の調査では、「あなたは商品にどれくらい満足しましたか?」と質問することが一般的です。NPSでは「この商品を誰かにおすすめできますか?」と具体的な行動について調査を行います。
顧客満足度では、顧客の現時点での感情しかわかりません。しかし、NPSでは将来的にどれほど顧客が増える可能性があるのか、把握可能です。
顧客の未来の行動を予測できる指標があれば、企業の業績予想や今後の施策考案に役立てられ、業績の向上に直結させられます。実際にNPSの提唱者によれば、「NPS®でトップを走る企業は、競合他社の2倍の成長率を上げている※」という調査結果も出ているようです。
あわせて押さえておきたい「eNPS」とは
NPSの関連用語として、企業が従業員から集めている愛着度や信頼度を表す「eNPS(Employee Net Promoter Score)」も押さえておきましょう。eNPSは、「家族や友人に自分の職場を勧めたいか」を尋ね、職場の推奨度を数値化する指標です。
eNPSを調査すると、離職リスクの高い従業員やエンゲージメントの高い従業員を正確に把握できるようになります。eNPSが高い従業員ほど、自社に愛着を持って意欲的に仕事をしてくれる傾向にあります。離職率や生産性を改善する際に有効な指標だといえるでしょう。
なるほど!NPSは企業の「これから」と関連が深い指標なんですね!
そうなんだ。顧客満足度も大切なんだけど、両方をうまく組み合わせて活用できるといいね。
ところで、NPSってどうやって計算すればいいんでしょうか?
NPSを簡単に分析・計算する方法

NPSを調査・分析する方法は、次のとおりです。
- NPSアンケートの設問を設計する
- NPSを計算する
- NPSを分析する
各プロセスの詳細をみていきましょう。
NPSアンケートの設問を設計する
まずは、NPS調査のために使用するアンケートの設問を設計します。NPS調査の基本は、「あなたがこの企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚にすすめる可能性は、どのくらいありますか?」という設問です。
しかし、その質問だけではどのような理由で回答を導き出したのかを把握できないため、NPSに影響を及ぼす顧客体験や顧客属性などの設問も追加します。次のような設問を追加しておくと、より詳細な分析に役立ちます。
NPSの設問例
- 1.次の項目が評価にどの程度影響を与えましたか?
「店舗へのアクセス」「商品の見つけやすさ」「接客品質」「ブランドのイメージ」「口コミ」 - 2.具体的な利用目的を教えてください
- 3.購入理由を教えてください
選択肢で回答する設問だけではなく、フリーコメントを記入してもらう設問も用意できると効果的です。必要な設問は商材やブランドによって異なります。商品の認知から購入後までの顧客体験・接点を整理し、NPSに影響を与える要素を見極めましょう。
NPSを計算する
アンケートを用いた調査が終わったら、NPSを計算して自社のスコアを確認してみましょう。NPS調査では、「あなたがこの企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚にすすめる可能性は、どのくらいありますか?」と質問して、0~10の11段階で解答してもらいます。各数値の分類は、次のとおりです。
- 0~6点:批判者
- 7~8点:中立者
- 9~10点:推奨者
上記のように分類し、「推奨者の割合(%)-批判者の割合(%)=NPS」の式で計算します。たとえば、自社の顧客100人に対して、9~10点が30人、0~6点が20人だった場合、「NPS=10」です。推奨者が多ければ数値は高くなり、批判者が多ければ数値は低くなります。
NPSを分析する
NPSを計算したあとは、なぜその結果に結びついたのかを分析します。設問とNPSの結果を分析すれば、「NPSが高いほど購入単価が高い」「顧客体験の中で接客がもっともNPSに影響を与えている」などの情報が導き出せるでしょう。各顧客体験がNPSにどう影響しているのかを分析できれば、具体的な改善策を見つけやすくなります。
へぇ~!NPSって意外と簡単に測定できるんですね!
そうそう。軸になる質問は1つだから、シンプルでわかりやすいよね。難しい調査が不要なのにメリットが多いから、NPSは注目を集めているんだよ。
へぇ~。NPSには、どんなメリットがあるんですか?
マーケティングでNPSを活用するメリット
マーケティングでNPSを活用すると、多くのメリットが得られます。マーケティングでNPSを活用するメリットは、次の3つです。
- 業績に直結する
- ポジショニングに役立つ
- 問題点を改善できる
各メリットを、詳しく解説します。
業績に直結する
NPSは、業績に直結する指標であると考えられています。なぜなら、推奨者の割合を調査できるNPSでは、次のような情報を把握できるためです。
- リピート利用の可能性
- SNSなどによる拡散の可能性
- 高評価レビューの増加割合
- アップセルやクロスセルの成功率
批判者や中立者と比べると、推奨者はリピート利用や高評価レビューを投稿する可能性が高まります。また、自社に好意的な評価を抱いている顧客であれば、購入単価の向上も見込めるでしょう。そのため、NPSと業績は連動していると考えられており、マーケティング活用の重要性が高まってきているのです。
ポジショニングに役立つ
ポジショニングとは、顧客に選んでもらうために、自社ならではの独自性を確立する戦略です。例えば、高級アイスクリームのハーゲンダッツは、厳選した素材とプレミアムなブランドイメージによりポジショニングに成功した商品の代表例です。
NPSを調査するときは、どの企業も同じ質問を使います。そのため、自社と他社を同じものさしで比較しやすくなる点がメリットです。
さらに、NPSに企業独自の設問を組み合わせれば、自社の優位性を数値化できるようになります。NPSの結果と各設問の結果はポジショニングに役立てられるので、競合に負けないマーケティング戦略を考案する際に役立つでしょう。
問題点を改善できる
NPS調査では、顧客を「批判者」「中立者」「推奨者」の3種類に分類します。それぞれがどれほどの割合で存在しているかを把握できれば、自社の問題点にあった適切な施策の考案につなげられます。批判者が多いときは、商品とサービスの両方に大きな欠陥があるかもしれません。
この場合は、商品やサービスの品質を調査すると問題を見つけやすくなるでしょう。中立者が多い場合は、「商品かサービスのどちらか一方に問題がある」もしくは「付加価値が十分でない」などの問題が考えられます。
丁寧な接客で顧客体験を高めるなど、中立者を推奨者に押し上げるための施策を考える必要があるかもしれません。NPS調査では自社の状態を正確に把握できるため、よりよいサービスの提供に活かせるのです。
ただし、NPSの数値だけで具体的な問題点を把握することは困難です。他の設問と組み合わせることで、自社に必要な改善策を見つけやすくなります。
マーケティングでNPSを活用するデメリット・注意点
マーケティングでNPSを活用することには、次のようなデメリットもあります。
- 調査方法で結果が変わる可能性がある
- 日本人の特性的にスコアが低くなる傾向にある
- 中小企業には不向き
各デメリットの詳細を説明します。
調査方法で結果が変わる可能性がある
NPSの調査方法はシンプルでわかりやすいものですが、手法によって調査結果が変わる可能性があるため注意しましょう。
例えば、「実名で回答する場合」と「匿名で回答する場合」、「過去半年以内に購入した顧客」と「過去3年以内に購入した顧客」では、NPSの結果は大きく変わります。NPSの測定時はもちろんのこと、他社の結果と比較するときも測定方法の違いに気をつける必要があります。
日本人の特性的にスコアが低くなる傾向にある
現時点でのNPSの測定方法ではアメリカにおける採点基準を採用しているため、日本人の感覚では低いスコアが出やすい点に注意しましょう。日本人は中間的な数値を選ぶ傾向があるため、ほかの国よりも数値が低くなります。
さらに日本人の場合、0~10の11段階で評価しようとすると、どうしても5を中間的な評価と捉えてしまいがちです。しかし、NPSでは中立者の評価が7~8となります。
そのため、マイナスのスコアになることがほとんどなのです。今後は、より日本人の特性に合ったNPSの測定方法を考えていく必要があるかもしれません。
中小企業には不向き
一般的にNPSは中小企業には不向きです。無料で一定数のアンケート結果を得られるなら、問題なく活用できるしょう。しかし、回答を集めるには、少なからずリソースが必要です。場合によっては、回答者にインセンティブを付与する必要もあります。
調査より、ひとりでも多くのお客様を増やすために、リソースやコストを投下したほうが良いケースもあるでしょう。NPSがわかったらからといって、すぐに売上になるわけではないのです。
もちろん、業種によっては企業規模に関わらずアンケートを回収しやすい場合もあります。NPSを活用したい場合は、企業規模ではなく、必要なサンプル数(最低400)を取得するためにかかる予算で判断しましょう。
めもめも……、勉強になります……。なんだか僕、NPSの活用戦略に興味がわいてきました!実際に調査してみようかな!
それなら、NPSを調べるときのポイントも知っておくといいかも!
NPSを調べるときのポイント

NPSを調べるときは、以下のポイントを意識しましょう。
- 競合他社のスコアを把握しておく
- なるべく多くのデータを集める
- 定期的に調査する
- 顧客を特定して測定する
- さまざまなシーンで活用する
各ポイントについて詳しく説明します。
競合他社のスコアを把握しておく
NPSを算出したら、結果を確認するだけではなく競合他社とスコア比較をしましょう。「NPS®(顧客推奨度)業界別ランキング※」など、さまざまな企業のNPS値を調査して公開しているサイトがいくつかあります。
自社と同じ業界で同じような規模の他社と比較することで、自社の優位性や課題を発見できます。ただし、限られた会社のNPSしか公開されていないので、必ずしも自社と似た立ち位置の企業が見つかるわけではないことを理解しておきましょう。
なるべく多くのデータを集める
統計学的な観点からいうと、NPSは400人以上に対して調査をすることが望ましいとされています。400人以上のサンプルの場合、誤差は±5%程度です。
なお、2,000サンプル以上の調査を行うと誤差を±2%程度に抑えられます。正確な結果を知りたい場合は、より多くの顧客に対して調査を行いましょう。
定期的に調査する
NPS調査は、定期的に何度も実施しましょう。数値の推移を時系列でとらえることで、成果につながる施策を実施できているか、どれほどの効果を得られているのかを知ることができます。
頻度について明確なルールはありませんが、あまりにも頻度が高いと顧客の負担になりますし、低いと施策の効果を正確に測定しにくくなります。半年もしくは1年に1度の頻度で実施することが望ましいでしょう。
顧客を特定して測定する
NPS調査を実施するときは、顧客を特定することをおすすめします。なぜなら、顧客層によってNPSの結果が大きく異なる可能性があるためです。属性情報や会員ランクなどの条件を特定して調査することで、どのような要素がNPSに影響を与えているのかをより詳しく分析できるようになります。
さまざまなシーンで活用する
単にNPSの数値を把握するだけでは、企業の成長につなげられません。NPSを測定したら、その結果を経営やマーケティング戦略に反映しましょう。NPSの結果は、次のようなシーンで活用できます。
- 商品やサービス内容の改善を検討するとき
- 今後のマーケティング施策を考案するとき
- アフターフォローや顧客対応の改善を目指すとき
- ブランド戦略を見直すとき
このように、NPSが活用できる場面は多岐にわたります。推奨者を増やして企業の業績を向上させるためにも、活用方法も考えたうえでNPSを測定していきましょう。
先輩、もしNPS調査の結果があまりよくなかった場合は、どんなふうに改善していけばいいんですか?
そうだね。改善点は企業によって異なるから一概にはいえないんだけど、こんな戦略はどうかな?
NPSを向上させる戦略・方法
NPSを向上させるための戦略は、「推奨者を増やす戦略」と「批判者を減らす戦略」の2つに分けられます。ここでは、各戦略におけるポイントを説明します。
推奨者を増やす戦略
そもそも推奨者の数を増やさなければ、NPSの向上は見込めません。推奨者の増加には、リピーターの増加や情報拡散による新規顧客の獲得効果があるため、優先的に取り組むことをおすすめします。
推奨者を増やすには、自社に強い愛着心・信頼感を抱いてくれるロイヤルカスタマーの育成が欠かせません。そのためにも、ユーザーのニーズに沿った商品・サービスの提供を心がけましょう。具体的な戦略としては、次のようなものが挙げられます。
- 商品やサービスの品質向上
- CRMの活用による関係性構築
- 有益な情報の発信
- 定期的なコミュニケーションやアフターフォロー
顧客アンケートやインタビューなどを実施して顧客の希望に耳を傾けると、自社に必要な施策がみえてくるでしょう。
批判者を減らす戦略
批判者を減らして中立者に変えることも、NPSの向上には有効です。批判者の減少には、顧客離れを防ぐ効果があります。批判者を減らすために、顧客が抱いている不満を調査し、迅速に改善しましょう。アフターサポートやカスタマーサポートに注力し、真摯にクレーム対応をすることも大切です。
ただし、一度マイナスのイメージを抱いてしまった批判者の考え方を変えることは、決して簡単なことではありません。あまりにも批判者が多い場合以外は、推奨者を増やす戦略に注力したほうがよい可能性があります。
改善点を顧客に周知する
NPSの結果に応じて何らかの改善を行ったときは、その内容を顧客に周知するという戦略も一案です。批判者の意見を受け止めて改善に取り組んでいることをアピールすれば、企業が真摯に対応していることを伝えられます。
顧客が期待する以上の対応ができれば、マイナスの評価をプラスの評価に転換することも可能です。また改善点の周知は、中立者や推奨者へのアピールにも有効です。「常に顧客を第一に考えてくれているな」「真面目な姿勢がもっと好きになった」など、さらなる評価向上に役立ってくれるでしょう。
NPSが公開されている企業はまだそう多くないし、企業によってサンプルにしているデータ数が異なるんだ。数値だけをみて一喜一憂しないように注意しようね。
わかりました、先輩!ところで、僕「日本ではNPSに意味がない」っていう意見を聞いたことがあるんです。それって、本当なんですか?
日本では「NPSに意味がない」って本当?
NPSの活用について、「日本では意味がない」と考える方は少なくありません。メリットが豊富なNPSですが、どうして「意味がない」といわれてしまうのでしょうか。ここでは、その理由と日本におけるNPSの活用ポイントを説明します。
「NPSに意味がない」といわれる理由
NPSは、もともと海外で生まれた指標です。そのため、日本人の国民性にはマッチしにくく、意味がないと考えられることがあります。日本人は、アンケートの際に中間的な評価をつける人が多い傾向にあります。
10段階評価のうち「9~10」をつける人は少なく、好意的なイメージを抱いていても無意識のうちに「7~8」を選んでしまうことが多いのです。日本においてはよい評価である「7~8」であっても、NPSでは中立者に分類されてしまいます。
さらに、中間的な評価である「5~6」でも、NPSでは批判者に分類されます。つまり、「実際の顧客の評価」と「NPSにおける評価」が大きく乖離してしまっているのです。
海外の企業では多くの企業がプラスのNPSを獲得しているのに対し、日本では業界トップの企業でもNPSのスコアはマイナスの数値になってしまうことがあります。
このように、海外と日本では評価に対する意識が大きく異なるため、海外の指標であるNPSの使用に意味がないと思われることが多いのです。
日本でNPSを活用するときに重要なこと
海外と日本では、NPSの数値が異なりすぎます。そのため、海外企業とNPSを比較したり絶対値を単体で見たりする活用法に意味はないでしょう。
しかし、NPSを調査する意味がまったくないということにはなりません。日本でNPSを活用するときは、次のようにさまざまな方法で数値を比較することで効果を発揮します。
- 同業他社比較
- 時系列比較
- ブランド間比較
- 商品間比較
- 顧客属性間比較
日本国内の企業や自社の実績と比較するぶんには、国民性の違いによる影響は受けません。そのため、数値がマイナスになったとしても気にする必要はないのです。NPSは、競合他社や過去の自社実績と比較し、よりよい数値にしていく取り組みのヒントとして活用することが大切です。
なるほどぉ~!海外の指標だからといって、海外の基準にあわせて評価する必要はないんですね。
そうそう。海外のNPSと国内のNPSは別物だととらえて、自社にあった活用法を確立することがポイントかな。
参考までに、日本でNPSを活用している企業の事例を紹介しておくね。
NPSの企業活用事例
日本国内でNPS調査を行っている企業は、どのように結果を活用しているのでしょうか。ここでは、2つの企業事例を紹介します。
楽天グループ
楽天グループは、全事業でKPIとしてNPSを導入しています。各事業内にNPS向上の責任を担う「NPSマネージャー」を配置し、サービスを横断して知見を共有する品質向上委員会を新設しました。NPSマネージャーから現場メンバーにNPS改善のノウハウが展開され、ボトムアップで新たな取り組みに成功。
さらに、それぞれの取り組みが委員会で共有され、他のサービスへ横展開されるという好サイクルが生まれています。NPSや顧客満足度は継続的に向上し、業界No.1である楽天カードに続くサービスが増えてきているそうです。
富士通株式会社
富士通株式会社では、従来行っていた「顧客満足度調査(CS調査)」を「お客様ネット・プロモーター・スコア調査(お客様NPS調査)」に変更。顧客との信頼関係を評価する「お客様NPS」を経営目標として定め、改善・向上を測っています。
2021年には+2.3ポイント、2022年には+18.1ポイントのお客様NPS向上に成功。世界中に点在する顧客から寄せられる要望や課題を収集し、同じ指標で評価・共有することで、顧客との良好な関係性構築に成功しています。
みんな、いろんな方法でNPS改善に取り組んでいるんですね!とっても勉強になりました!
参考になったみたいでよかったよ。ビギニャー君も、これからはNPSを積極的に活用してみてね。